

ニュース
MENU


2019.11.01税務ニュース
令和2年から大きく変わる所得税
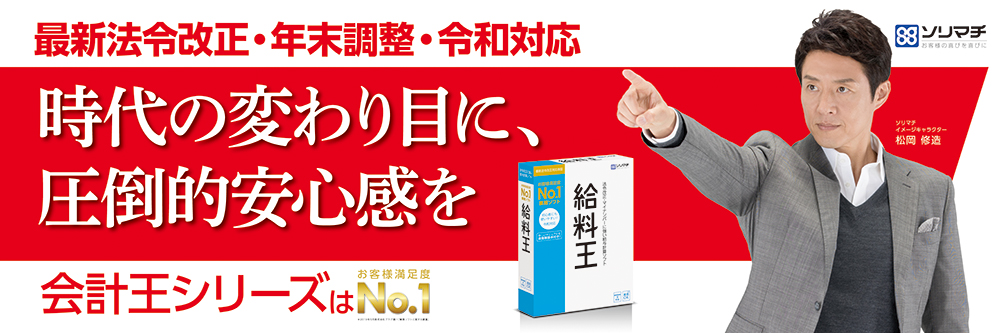
令和元年も残すところあとわずか。
税金のトピックとして令和元年では消費税増税がその主役でした。税率が10%に上がったのはもちろんのこと、今までなかった軽減税率が導入され税務の現場では慣れるのにまだ時間がかかりそうです。年末が近くなってくるこの時期、税金の話題は「税制改正」が大きく取り上げられます。例年の流れでは、12月中ごろに税制調査会から次年度の税制改正の内容が公表され、年明けの国会で可決承認されるからです。ただ、この最新の税制改正の内容は、すぐに私たちの生活に影響を与えるわけではありません。改正された税制が実際の税務の現場で使われるようになるには、一部の例外を除き数年後というのが多いのです。例えば、令和2年度税制改正の内容が実際に適用されるようになるのは、令和3年度以降というのがほとんどです。つまり、次年度私たちの生活に直結してくる税制改正の内容は、実は数年前の税制改正により承認された内容になるのです。
令和2年は所得税が大きく変わる
令和2年から大きく変わる税金の代表が「所得税」です。所得税は毎年の税制改正で少なからず変わっていますが、来年からは基本的な数字が大きく変わるのです。メインの改正内容としては、平成30年度で改正されたものが来年から適用されることになります。影響が大きな項目としては
- 給与所得控除の引き下げ
- 公的年金等控除の引き下げ
- 基礎控除の引き上げ
の3つが挙げられます。
所得税の計算は、所得金額から各控除金額を差引いて行われます。この3つの改正項目では、それぞれ「控除」の金額が見直されています。控除額が引き下げられる、ということは税額が増える、すなわち「増税」となります。一方、控除額が引き上げられる、ということは税額が減る、すなわち「減税」となります。
改正の具体的な内容としては、給与所得控除と公的年金等控除については、現在の控除額からそれぞれ10万円引き下げることになり、基礎控除については控除額が10万円引き上げられることになります。3つの所得控除のうち、2つが増税、1つが減税ということになります。
税額への影響は?
そこで、気になるのが税額への影響です。例えば、サラリーマンの方で給与所得しかない方については、給与所得控除が10万円減り、基礎控除が10万円増えることになりますので、プラスマイナスゼロで税額に影響が出ることはないように思えます。また、公的年金しかもらっていな方は、公的年金等控除が10万円減り、基礎控除が10万円増えることになりますので、こちらもプラスマイナスゼロで税額に影響が出ることはないように思えます。
大多数の方が今回の改正によって税額に影響は出ないはずですが、実は一部の方は影響を受けることになるのです。その謎を解き明かすためには、今回の税制改正の内容をさらに細かく見ていく必要があります。給与所得控除については、その控除上限額の収入金額を850 万円とし、実際の控除上限額は195 万円(現行220万円)に引き下げられることになりました。公的年金等控除は、その収入金額が1,000 万円を超える場合の控除額については、195 万5千円の上限を設けられました。基礎控除については、現行は一律38万円の控除を受けることができましたが、今回より以下のように所得により制限が加えられるようになりました。
基礎控除額の改正内容
合計所得金額が2,400 万円を超える人はその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500 万円を超える人については基礎控除の適用はできないこととする。
合計所得金額が 2,400 万円以下である個人 48 万円
合計所得金額が 2,400 万円を超え 2,450 万円以下である個人 32 万円
合計所得金額が 2,450 万円を超え 2,500 万円以下である個人 16 万円
表面に出ている数字だけを見てみると、最終的に影響がないように思える内容も、細かく見ると、大きく変わることがよくわかります。この改正によって影響を受け増税となるのは、いわゆる富裕層で所得が大きい方です。例えばエリートサラリーマンで給与収入3,000万円程度の方であれば、給与所得控除の金額は少なくなり、基礎控除は一円も認められないことになるのです。
どう対応するのか?
富裕層にとっては受難ともいえそうですが、これらにどう対応するのか、その対応策を知りたいという方も多いはずです。しかし、現在の税金の世界では一発逆転というのは、難しいのも事実です。従来から言われていることですが、節税を考えるときに、なにか大きな対策ひとつで対応するのは無理があります。細かな対策の積み重ねをすることによって、無駄な税金の支払いを極力抑えるという方法が望ましいです。所得税では各種控除を無駄なく適用させることが考えられます。例えば、平成31年改正の内容で、住宅ローン減税が拡充されています。また、副業を認める会社も増えており、その際に「事業」として副業をする方もいると思います。その場合、事業では収入を得るためにかかった経費については控除が認められていますので、それらの利用も検討してみると良いでしょう。税法の穴をくぐるのではなく、認められた方法で細かく節税することをお勧めします。そのためには、情報収集を怠りなく行っていくことが大切です。
[myphp file=writer019]




 トップ
トップ
